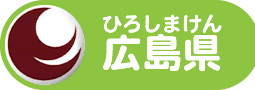| 面積 | 8,480km2(全国11位) |
|---|---|
| 人口 | 約285万人(全国12位) |
| 人口密度 | 336人(全国18位) |
都道府県豆知識
- 位置と概要
- 地形と自然
- 気候
- 産業
- 観光
- 県名の由来
- 境界線の策定にまつわる話
- 県庁所在地について
- なんでもお国自慢
位置と概要
広島県は,中国地方の中央に位置する。北は島根県と鳥取県,東は岡山県,西は山口県に接し,南に面する瀬戸内海には百数十の島々がうかんでいる。近畿地方と九州地方とを結ぶ瀬戸内海の中心にあるため,むかしから海や陸の交通で重要な役割をはたしてきた。
人口は広島市の北部や廿日市市,大竹市などの瀬戸内海沿岸に集中している。
地形と自然
北部には中国山地が走り,東部には平らな吉備高原が広がる山がちな県で,その間には三次盆地がある。また,中国山地からは,太田川,沼田川,芦田川などが流れ,南の瀬戸内海にそそいでいる。入り組んだ海岸線の近くには,大小さまざまな島がうかび,そのうちの百数十の島が広島県に属している。
気候
中国・四国地方で最も広い面積を持つ広島県は,南北で気候に大きなちがいがある。南部の瀬戸内地方は,中国山地と四国山地にはさまれているため,季節風の影響が少なく,温暖で雨も少ない。 一方,北部の中国山地沿いは,冬の寒さがきびしく,1m以上も雪が積もることがある。
産業
産業別人口の割合は,第一次産業3.3%,第二次産業25.3%,第三次産業66.6%。第三次産業で働く人の割合が多く,第一次産業で働く人の割合は少ない。
農業は,北部や中部で米作りや野菜の栽培,畜産が行われ,また,温暖な瀬戸内海の島々では,ミカンの生産や野菜の促成栽培が行われている。沿岸部では漁業がさかんで,とくに養殖のカキの生産量は,全国で最も多い。 広島市は中国・四国地方の経済の中心都市で,また,呉市は戦前から造船や鉄鋼業で発展してきた。
観光
広島市の原爆ドームと廿日市市 [旧宮島町]の厳島神社は,世界文化遺産に登録されている。元安川東岸にある原爆ドームは,もとは産業奨励館という建物で,ここからおよそ150mはなれた上空で原爆が爆発したといわれている。 また,ドームの南側にある緑ゆたかな平和公園には,原爆死没者慰霊碑,平和記念資料館,原爆の子の像など,平和への祈りをこめてつくられた多くの建物や碑がならんでいる。平和記念資料館には,原爆が落とされた時の資料が展示され,日本全国から平和をねがう人々や修学旅行生がおとずれる。厳島神社は,今からおよそ1,400年前につくられたといわれ,その後,平清盛の時代に建て直された。貴族の住宅の建築様式である「寝殿造」の建物で,日本三景の一つとして知られている。
県名の由来
「広島」という地名が使われるようになったのは,戦国時代の武将・毛利輝元が,安芸の国を支配するため,太田川の河口に広島城を築いた時にさかのぼる。城がおかれた中州には,当時五箇荘と呼ばれる村があったが,その中州が大きく広い島であったところから「広島」と名づけられたといわれている。 「広島」は,江戸時代に藩の名前となり,明治時代の廃藩置県の時に県名となった。
境界線の策定にまつわる話
明治4(1871)年の廃藩置県によって広島県が誕生すると同時に,広島県以外にもいくつかの県がつくられた。 現在の福山市のあたりは福山県,岡山県倉敷市のあたりは倉敷県,山口県岩国市のあたりは岩国県というように,当時の県域は,現在よりも細かく分かれていた。その後,何回かの吸収や合併をへて,明治9(1876)年に福山県と倉敷県の一部が広島県に加わり,現在の県域が確定した。
県庁所在地について
広島県の東側は,廃藩置県の後しばらくは岡山県であったため,県庁である広島市は,県の西側に位置する。第二次世界大戦中に原爆で破壊された広島の町は,戦後,核をなくし平和をうったえる都市へと生まれ変わった。 昭和55(1980)年に全国で10番目の政令指定都市となり,昭和60(1985)年には100万都市となった。現在,広島市は,中国・四国地方の中心都市として発展し,国の機関や,企業の支社や支店が集中している。
なんでもお国自慢
世界遺産
宮島の厳島神社は,宮城県の松島,京都府の天の橋立とあわせて「日本三景」の一つに数えられ,原爆ドームとともに世界文化遺産に指定されている。
養殖業
広島湾で養殖されるカキの生産量は,全国のおよそ70%をしめている。他に,海苔の養殖なども行われている。
なんでも日本一
- 路面電車の年間輸送人員および保有車両数日本一(平成24年 広島電鉄)
- 手縫い針の生産量日本一(広島市)
- ソースの購入量日本一(広島市 平成23~25年平均 都道府県庁所在市別ランキング)
- かきの購入金額日本一(広島市 平成23~25年平均 都道府県庁所在市別ランキング)