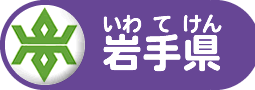| 面積 | 15,279km2(全国2位) |
|---|---|
| 人口 | 約130万人(全国32位) |
| 人口密度 | 85人(全国46位) |
都道府県豆知識
- 位置と概要
- 地形と自然
- 気候
- 産業
- 観光
- 県名の由来
- 境界線の策定にまつわる話
- 県庁所在地について
- なんでもお国自慢
位置と概要
岩手県は,東北地方の北東部に位置する。西は秋田県,北は青森県,南は宮城県に接し,東は太平洋に面している。面積は北海道の次に大きく,香川県をのぞく四国の面積とほぼ同じである。
面積は広いが平地が少なく,また厳しい気象条件もあって,人口密度は,全国で北海道についで2番目に低い。全国有数の農業県で,県の主な都市は北上盆地にあり,人口の大半がここに集中する。人口は30年前に比べるとほぼ横ばいで,三陸沿岸や北上高地にある町村は,深刻な人口減少と高齢化に悩まされている。
地形と自然
岩手県の大半が山地や高地で,平地が少ない。秋田県境を奥羽山脈が,その東側には北上高地がともに南北に走り,その間を南に流れる北上川にそって北上盆地がひらけている。県の北部には岩手山や八幡平などの火山がそびえる。 太平洋側は全長600kmにおよぶ三陸海岸が続き,南側は典型的なリアス海岸である。複雑にいりくんだ海岸線は,美しい景観と宮古や釜石などの天然の良港をつくりあげている。
気候
太平洋側の地域は,冬でも雪が少なく,比較的暖かい好天にめぐまれる。中央部の北上盆地では,夏の気温が上がり冬の寒さが厳しい内陸性の気候を示す。 初夏には,「やませ」という冷たい北東風がふき,気温が上がらず,農作物に冷害をもたらすことがある。西部の奥羽山脈の一帯は,冬に積雪が多い。
産業
産業別人口の割合は,第一次産業12.0% 第二次産業24.2% 第三次産業62.3%。第一次産業で働く人の割合は,東北地方では青森県と並んで多い。
農業の中心は,北上盆地の稲作と北上高地の畜産である。米づくりがさかんに行われている北上盆地は,冷害の影響を受けやすく稲作に適しているとはいえなかったが,品種改良や栽培方法の工夫により収穫量が増えてきた。また,なだらかな高原の続く北上高地では牧草や飼育作物が栽培され,広大な放牧地では,乳牛や肉牛,豚やブロイラーが飼育されている。
岩手県では,農業だけでなく漁業もさかんである。三陸海岸沖は,暖流と寒流がぶつかる良い漁場で,宮古や釜石,大船渡などの漁港は,水あげ量が多いことで知られる。また,リアス海岸の入り江は波静かで,ワカメ,コンブ,ノリ,カキなどの養殖がさかんに行われている。
観光
岩手県は自然が豊かで,日本のふるさとといっても言いすぎではないほどの雄大で美しい自然が残されている。西部には南北に高くけわしい奥羽山脈が走り,いたるところで温泉がわく。また十和田八幡平国立公園もある。 一方,東側の太平洋岸には,「海のアルプス」と呼ばれる断崖絶壁やリアス海岸の連なる陸中海岸国立公園がある。県内の山岳地域と海岸地域に,全くちがった特徴を持つ2つの国立公園があることが,岩手県のみりょくである。東北自動車道や東北新幹線が開通したこともあり,訪れる観光客も年々増えてきている。
県名の由来
明治3(1870)年,廃藩置県が行われる一年前に,盛岡藩は盛岡県と名前を変えた。さらに2年後の明治5(1872)年,県庁所在地である盛岡のあった「岩手郡」の郡名をとって,「岩手県」と改名された。廃藩置県を,政府の方針より一年も早く実施し県名を変えた理由は,明治政府に従う姿勢を示すためであったといわれている。 盛岡藩は,戊辰戦争に参戦して敗れ,「朝敵」「逆賊」の汚名を受け,厳しい処分を受けていたのである。
境界線の策定にまつわる話
江戸時代,現在の岩手県の範囲には,盛岡藩をはじめ,南には仙台藩,一関藩,北には八戸藩があった。現在の岩手県が誕生するまでの経過はとても複雑で,今の岩手県が成立したのは,廃藩置県から5年が経過した明治9(1876)年のことである。 その間に10回以上も行政区画が変わった。最終的には,南部の郡は宮城県へ,北の胆沢郡・江刺郡・磐井郡を岩手県に編入し,さらに宮城県から気仙郡を編入し,また青森県から二戸郡を編入して,現在の岩手県が成立した。
県庁所在地について
盛岡の起こりは,江戸初期,南部氏がこの地に城を築いたことに始まり,南部20万石(初めは10万石)の城下町としてさかえた。 廃藩置県により岩手県と改名された時にも,県庁は盛岡におかれ,そのまま現在にいたっている。
なんでもお国自慢
民話のふるさと
北上盆地にある遠野は,古くから宿場町として栄えたところである。明治時代の民俗学者・柳田国男は,遠野の人々の間に昔から語り伝えられていた山の神,家の神,天狗,河童などをめぐる伝承・伝説などを「遠野物語」としてまとめた。「遠野物語」に登場する地名は,現在も数多く残されており,毎年多くの観光客が民話の舞台を訪れる。
小岩井農場
岩手山南部のふもとにあり,面積約3000ヘクタールもの広さをほこる。明治24年から開墾された広大な放牧地では,2000頭以上の乳牛のほか,多くの羊やにわとりなどが飼育されている。農場には,乳業工場や酪農資料館もあり,牛乳やバターができる様子を見学することができる。
なんでも日本一
- 自然海岸率日本一 (全海岸線の約80%)
- ホップの生産量日本一
- ワカメの生産量日本一
- 透明度日本一の龍泉洞水深98m,透明度41.5m 国の天然記念物
- 豆腐の購入数量日本一(盛岡市 平成23~25年平均 都道府県庁所在市別ランキング)